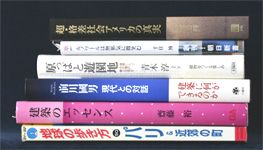2006�N10��31���i�j
�@9:00 �߂��Ƀz�e�����o��B��������A�����������v�����w�h�g�Ȃ̂͂Ȋفh�����w�B�ו��̃f�U�C���ɂ������������Đv���Ă��邱�Ƃ��`����Ă���B
�h���{�݂�X�g�����Ȃǂ����邪�g���Ă���C�z�͂Ȃ��B�{�݉^�p����Ȃ��₳��Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@����A�����p�ق̐��ʎʐ^���B�e���悤�Ƃ������A�Ԃ����сA�ʐ^�B�e���ł��Ȃ������̂ŁA������x�A�����p�ق̐��ʎʐ^���B��ɍs���B
�@���̌�A���ނ���فu���y�v�̍��ނ�����֍������s���A�R���A�����Ă̓����ł���B�ߑO���̂������l�����Ȃ��B���Ȃ������C�����������ł���B
�R���ԂłS��A���ނ�����ɓ��������ƂɂȂ�B10:00 �߂��I�����ċA�r�ɂ��B�w�h�s�ŃK�\���������邪159�~�^���b�g���ƍ����Ȃ̂łQ�O���b�^�[���������B
�r���A���̉w��`���Ȃ���̂�т�ƁA�A��B16:00 ���
�����p�فiꠕ��F�j

|

|
�Ȃ̂͂Ȋفi���萳���j

|

|

|
2006�N10��30���i���j
�@7:00 �N���@�э]�p�̌������ɂ͑�G�����̗Ő���������B�ɂ₩�ȋȐ��A�������Ȑ��A�F��ȕω��̂���Ȑ��ō\�����ꂽ�Ő��������Ă���B
�Ő����D�萬���R�X�̌i�ς͑Ί݂̑�G��������F�����������Ă��������낤�B
�����R�����قǕ�炵�����茧���]���猩�����i���v���o���B�R�̒a�������}���鍠������Q�����R���̍����낤�A
�̉Ԕ��̌������ɗL���C�̊C���L���L���ƋP���A����Ɍ������ɂ͍��肩��E��ɂ����āA�����x�̗Ő����ŏ��͊ɂ��A
�����ď��X�Ɍ������Ő��ɕω����Ă����B���F�̔��ƁA�L���L���P���C�ƁA���F�̎R�Ƃ��̗Ő��A���̋L���̕��i���v���o���B
�������͖k��B�ɔ�ׂ�ƌ����_�炩���B���̏_�炩�����������ȕ��i�̐F������ω������Ă���B��F�̕��i�͖k��B�ɂ͂Ȃ����l�ȐF�̕ω���������B
���̂悤�Ȍb�܂ꂽ���R�����͐l�̊�������Ă鎞�ɕK���e����^����͂��ł���B�э]�p�����ޓ�F�Ɉ�����l�͑��ɂ͂Ȃ������������Ă���͂��ł���B
�@9:30 �z�e�����o���A�܂��͊��z�e���i���w�h�ό��z�e���j�ɂ�������p�قɌ������B�v���U��̖K��ł��邪�z�e���~�n�͊ՎU�Ƃ��Ă���B
�����p�ق�ꠕ��F���v�������p�قł���B�Q�x�K�ꂽ���Ƃ��邪�A�O��̖K�⎞�Ƌ�Ԃ̔c�����قȂ�B
�L���̒��ł̓X�e�b�v�A�b�v���Ă�����Ԃ̋K�͂����Ȃ�傫�����������ł��������A����̓X�e�b�v�A�b�v���Ă�����Ԃ͂���قNj���ɂ͊������Ȃ������B
�������Ȃ���A�ޗ��̎g�����A�ޗ����ӏ��Ƃ��Ăǂ̂悤�Ɍ����邩�Ȃǂ̏ڍׂ͖ڂɓ����Ă���̂ł���B
��t�Ŏʐ^�B�e�̋������炤�ƎB�e�\�Ȃ̂Łg���̂��߁h�Ɨ��R������������������B�Ȃ��A�������̊G������A����Ȃ�̈�i�����W�W�����Ă���B
�@10:30 ���p�ق��o�ĎR��`�������B�����m�ɖʂ����g�R�썻�ނ�����h�ɓ���B�����̍��ނ�����͋q�����炸�A�ݐ؏�Ԃł���B�O�m�ɖʂ��Ă��邹�����A�g�̉����Ȃ��牡�ɂȂ�B������̂͐����������ł���B
�g�ł��ۂł̓����͎��Ɏ����B�������P�O��������Ƃō����甇���o���A���𗬂��ďI���B
�@����������B����́g�����Z���^�[�h�Œ��H�B���̃g���̎h�g�𖡍����B���̌�A�V�Ái�ڂ��̂j�������B
�ȑO�K�ꂽ���͋�����\��܂̎R���̓����z�����v���o�����邪�A���̓J�[�u�̖����L�����H���ł��Ă���B�����z���g���l�����E�E�E�E�E�I�b�Ƃ��ƂƁA�s���߂��鏊�������B
�g���l�����ł��Ă���̖̂ʉe�������Ă���B���[�^���[�[�V�������i�ς܂ł��ς��Ă����B�V�Âɂ͐l�e���Ȃ��썑�I�Ȑ̖̂ʉe�͂Ȃ��Ȃ��Ă���B�ŏ��A���̏W����K�ꂽ���͊������o�������̂ł������B
�w�h�֖߂�A�������o�g�̍����������v�����w�h�g�Ȃ̂͂Ȋفh�����w�B�����������v���錚�z�͂��݂Ă��s�v�c�ł���B�F�{���ʖ��s�̋ʖ��W�]��A���������P�k�V���ٓW�]��Ȃǂ̍�i������B������̍�i���������������Đv���A�������������Č���Ǘ����錚�z�Ƃ��낤�B����ł͑Ë����Ȃ��Ǘ��̊�Ɍ��z���ł����ł��낤���͑z���ł���B
16:00 �߂��ɁA���ނ���فu���y�v�̍��ނ�����֓���B�A�g�s�[�Ɍ����ƌ��\�����ɋL����Ă��邪���̃A�g�s�[�͎��܂肻���ɂȂ��A�������͂Ȃ��������B
2006�N10��29���i���j
�@9:30 ����o���@13:20 �������s�V���ْ��@���[��������T�����A���x���s�������Ƃ̂���A�[�P�[�h�[�́g���ނ炳���h�ɓ���B
���[�������̖˂͔������F����ʓI�ł��邪�A���̃��[�������̖˂͑f�˂݂����Ȕ����ۂ��˂ł���B���܂��ɁA�����V�ł͂Ȃ��L���x�c�������̂������Ă���B�ȑO���������Ƃ̂��鑼�̎F�����[�����̃��[�������̓����V�����Ȃ葽�������Ă��āA���\�����ۂ����[�����������o��������B
�ŁA�g���ނ炳���h�̃��[�����̖��̓X�[�v���������肵�Ă��āA���������Ɩ����v���o���Ȃ��Ȃ�悤�Ȃ��̂ł���B
�@�������炦�Ŗ���������A�A�[�P�[�h���u�����B�������֗��ď��������Ă����v�����́A�������̏����͉���̏����Ɏ����A������щz���ăt�B���s���̏����ɋ߂��B����A����̏����͓쑾���m�́A�Ⴆ�A�p�v�A�j���[�M�j�A�n��Ȃǂ̏����Ɏ��Ă���A�ƁB
�Ñ�̖����̈ړ��͕s���ȓ_���������A���̓y�n�̐l�Ԃ��ǂ��̓y�n�̐l�ԂɎ��Ă���̂��햯���w��厖�Ȃ��ƂŁA�Ⴆ�ΏH�c���l���V�A�̈�`�q�ɋ߂��Ƃ�������������̂ł���B
�@14:00�߂��Ɏ������s�𗣂�w�h�������A15:30 ���B���������g���ނ�����h�ɓ��邱�Ƃɂ���B����̖ړI�͌��z�̌��w�͌����܂ł��Ȃ����A�g���ނ�����h�ł̓������ړI�̈�ł�����B���ނ���فu���y�v�͎w�h�s�������W�N�Ɍ��݂��A�i���j�w�h����܂��Â�����Ђʼn^�c���Ă���A����Ό��c�̉���قł���B
�g���ނ�����h�͊C�݂̍��n�̉���M����������Ă��邱�Ƃ���A�l�Ԃ����ɓ���Ƒ̓����x���T�O�x�߂��܂ŏオ��ƌ����Ă���B
�g���ނ�����h�ɓ��鎞�Ԃ̖ڈ��͂P�O���O��ƌ����Ă���B���̏�ɑ̂��������A���̏ォ�獻�������Ă��炤�̂����A���ɓ����ĂT�������Ȃ������Ɏ��A����̌��ǂ��h�N�I�A�h�N�I�Ɣg�ł悤�ɋ����B
�w�����M���Ȃ芾������Ă���̂�����B
�P�O�����ō�����N���o�āA�����������ق������B���Ɗ��𗬂��ďI���A�̂��y���Ȃ��������ł���B�z�e���������B�z�e���ł͎c�O�Ȃ���C���^�[�l�b�g�ڑ����s�ł���B0:00�A�Q
2006�N10��28���i�y�j
�@���͎����K�u���݂�����ł͂Ȃ����A�A���R�[������������͐������A���A�N�������͖ڂ��[�����������ŁA�ڂɃA���R�[�����c���Ă���悤���B
�̂����̂��x�X�g�Ȃ̂ŎԂ��Ԃ���Ɩڂ̈�a���͂Ȃ��Ȃ����B
�@14:00 �߂��Ɍ������s���B����A�R�N���̍K�N���������ă��[�N�V���b�v�̐i����������Ă�������̂ŁA��d���ς܂�����A
�����������������B�ނ�͑����������̂QF�ō�Ƃ����Ă���̂ł���B�݂�Ȃ��������̂ŁA��Ƃ̐i�ߕ��̒��ӂ�^����B
�������l�������Ƃ��q�ϓI�ɕ]�����āA���l�̖ڂł݂邱�ƁB�������ǂ��Ǝv���Ă����l���]�����Ȃ�������]���ɒl���Ȃ����ƁB�������D���Ȃ悤�ɍl����̂ł͂Ȃ��A���l������v�����Ă���̂��H���l���邱�ƁB
�����̍�i��s�ׂ��q�ϓI�ɕ]�����邱�Ƃ��ł���A�����Ɍl�̐���������B�g�v�����h�ł͂Ȃ��A�����W�J������悤�Ɍv��̒��Ƀh���}�̓W�J���l���邱�ƁB
��҂����́g�D���Ȃ悤�ɍl���Ȃ����h�A���邢�́g�D���Ȃ悤�ɂ��Ȃ����h�Ƃ��������Ĉ���Ă����̂ŁA�g�D���Ȃ��Ɓh���l���Ă��g�v�����h�Ŏ~�܂��Ă��܂��̂ł���B
�g�D���Ȃ悤�ɂ��Ȃ����h�Ƃ��������́A�e�̋����A���t�̋������v���O�������������Ă��Ȃ��������Q�ݏo���Ă���B
�g�D���Ȃ��Ƃ����Ȃ����h�A�Ƃ����͔̂@���ɂ�������̂悳�����Ȍ������ł��邪�A���̂悤�ȕ�����̂悳�����Ȍ����������邩���҂����͖����Ă��܂��̂ł���B
�v���O�����𗧂āA�n���I�Ɏv�l�ł��邱�Ƃ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���B���[�N�V���b�v�܂łP�T�Ԃ��Ȃ��B�ނ�ɂ͊撣���Ă��炢�����B�����Ɛ�������͂��ł���B
2006�N10��27���i���j
�@�؍��̓�����w�̋���������d�b������B������d�b������AJIA�̃��[�N�V���b�v�ɍ�����ł��Q���ł��Ȃ����A�Ƃ̖₢���킹���������̂ł���B
�������JICA�Ȃǂɏh���̉ۂ��ʂ̃z�e���Ȃǂ̖₢���킹���s���Ă����Ƃ���ł������B�����̓d�b�ŁA������w���z�w���Řb�����������ʁA����͎Q���������킹��A
�Ƃ������Ƃł������B�������Ƃ͂T�N�ȏ�̕t�������ł��邪�A���N�͎Q���̐\�����݂��Ȃ������̂ŐS�z���Ă����̂ł���B
�P�Q���Ɋw���Ɨ�������\��ŁA��������܂͓d�b�������A�Ƃ������ƂȂ̂ŁA���̎��͐F��Ȃ��Ƃ�b���������݂����B
�@18:30 ����X�e�[�V�����z�e�����q�ŌF�{��w�y�،��z�w�Ȃ̓�����ɏo�ȁB�F�{��w���猚�z�w�Ȃ̈ɓ��d���搶�A���y�̔����S�O�搶�����o�Ƃ��ďo�ȁB
������ɏo�Ȃ���ƐF��ȏ������̂Ŋy���݂ł���B�Q����̓��[�K�E���C�����z�e���̍ŏ�K�̃��E���W�ɏꏊ���ڂ��B�ɓ��搶�͎�����w�@�����������͖����w�����������A�����������̏o�g�ŋ��m�̒��ł���B
�ɓ��搶�͖��ăM���V���Ő_�a�̔��@����������Ă���A�M���V���ɍs�������͍ו��܂ňē����Ă����Ƃ̎��ŁA��x�͔��@��������w���Ă݂����Ǝv���Ă���B
�M���V���_�a�ɂ��ĐF��Șb���f���A���Ɋy�����ЂƎ����߂������B24:00�߂��ɋA��A�v���U��̌ߑO�l�ƂȂ����B
2006�N10��26���i�j
�@���A�e�n�̍��Z�ŁA�K�{�Ȗڂ̐��m�j���w���Ȃ��ŎɕK�v�ȉȖڂ��w���Ă��邱�Ƃ����o���A���Z�������Ƃł��Ȃ����Ƃ���艻���Ă���B
���I����@�ւ��\���Z�����Ă���̂ł���B�����̒�����ы���Z���l�ߍ����������Ă���悤�Ɍ����Ă��邪�A���́A
�������Z�̕����\���Z�����A�l�ߍ�������s���Ă���̂ł���B�_���؋��A��ы���̍��Z������̖��̒��ŃN���[�Y�A�b�v����Ă��Ȃ��B
�����������Ă��鍂�Z�͌����̒����ǂ��̐i�w�Z�ł͂Ȃ����B���������Q���Ă��鍪���͎��͍����ɂȂ��Ă���K�{�Ȗڂ������Ȃ������A���炪�w���v�j�ɑ������}�j���A������������ɂ���̂ł���B
�@�����A���{���z�j�̍u�`���s�������A�ŋ߂͎��Ƃ̐i�ߕ��������ς��Ă���B���́A���R�m���Ă���Ǝv���鎖�ł��m��Ȃ��A�Ƃ����O��ɂ����čׂ����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�����́A�u�`���̎���͊F���Ȃ̂����A�����́u�搶�I�@��Ԃ̒����͂ǂꂭ�炢�̒����ł����H�v�Ǝ������B�ȑO���Ɓu�H�v�Ǝ����������̂����A�����́g�H�h�Ǝv���܂ł��Ȃ����J�ɐ���������B
�u���吶�̓o�J�ɂȂ������v���ԗ����ɏ����Ă���悤�ɁA���吶�͎D�y���瓌���܂ʼn��L������̂��m��Ȃ�����o�J���ƁA
�i�������H100k��������5000�����ȏ�Ɠ������w��������A�Ƃ����b�������Ǝv�����E�E�j�����|�ŏ�����Ă��������A
���吶����ł͂Ȃ��A���̎�҂͒m���Ă����ē��R�̂��Ƃ�m��Ȃ��߂���̂ł���B�D�y���瓌���܂Ŗ}�����L������̂��m��Ȃ��͓̂��吶����ł͂Ȃ��B
�ŋ߂͒m��Ȃ��Ă����R�̎���ł���B��҂����ɐ������������Ȃ��Ă���̂ł���B
��l�����́g���R�m���Ă�����̂Ƃ��āh�C�ɂ��~�߂��ɘb����i�߂邩��A
��҂����͑�w�̎��Ƃ���łȂ��A������ݍ��b�ɑ��Ă͎��̓`���Ղ�J���v���ł����ς����Ȃ��̂ł���B���͈�ԁA��ځA�ꐡ�̒������w�������ɋ��������A��Ŏv���ƁA
�ꕪ�̒����ɂ��āA�ǂݕ��ƒ����������Ă��Ȃ��������ƂɋC�t�����B���T�⑫�������悤�B���̗l�Ȃ��Ƃ͖{�w�����̖��ł͂Ȃ��A
���Z���\���Z�����Ă��邱�Ƃɗ��Â������悤�ɁA�`������⍂�Z�ɂ����āA�����čs����ŕK�v�Ȃ��̂������Ă��Ȃ����Ƃ��傫�Ȍ����ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�m��Ȃ��Ă����R�̎���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l�����Ď�҂����ɑΉ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����C��t���悤�B
2006�N10��25���i���j
�@��T�Ɉ����p���A�Q�����ڂ����ƌ����̒��Ԕ��\�ł���B�����̔��\�͑��Ɛv�̔��\�ł���B�S�N���ɂȂ��Ă��łɂU�������߂��Ă���̂����A
�i���͎��ɒQ���킵���ł���B������A���͎�҂����ɂ��āu�S�������v�A�u�m���������v�A�u�����������v�́g�O�����h�ƌ����Ă��邪�A
���\�͐��Ɂg�O�����h��I�悷�錋�ʂƂȂ����B�m�����z�����悤�Ƃ��Ȃ��A�܂��Ă�n���͂�g�ɕt����Ȃ�Ă܂������O���ɖ����ł͓��e�̂���v�͂ł��Ȃ��̂ł���B
�\���͂Ƃ����Z�p�͂����Ă��A�\�����郂�m���Ȃ��Ɠ��e�̂���v�͂ł��Ȃ��B�����A�n���͂̏d�v���ɋC�t���Ă���w���͊F���ł���B
�������Ė��m�̂��̂ɐG��A�����������鎩���łȂ��Ƃ����Ȃ��B�{��ǂ�ŁA�l���A�����Ė��m�̂��̂𗝉��ł��鎩���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
��҂����͐�͂��ȓ���]�������Ă��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��B
�@�ߌ�͓��{�w�p�U����ɒ�o����u�Ȋw������v�̐\�����쐬�ɏI�n���邪�A16:30 ���狳����c�ł���B
�u�Ȋw������v�̐\�����쐬�͎��ɑ�ςŁA�\�����̕��͂������A�o���\�Z�����ċL���A�����𗠕\�ɃR�s�[���A�Еt�����Đ��{�����Ďd�グ��B�����ɁA�C���^�[�l�b�g�œ��{�w�p�U����ɓo�^���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�W�����č�Ƃ�i�߁A16:30�Ɋ�������o����B��x��ċ�����c�ɏo�ȁB20:30 �I��
2006�N10��24���i�j
�@���x�ݎ��ԂɂR�N������������BJIA�̃��[�N�V���b�v�ɎQ�����Ă���w�������ŁA����̃v���E���[�N�V���b�v�̕ɂ����̂����A
�l���Ă��钆�g�ɂ��Ă͕������Ԃ��Ȃ��B���炾��Ɩ��Ӗ��Ɏ��Ԃ��₷���Ƃ����͔�����悤�ɒ��ӂ���̂݁B
���Ԃ̎g��������肭�Ȃ��Ăق����B�R���y��[�N�V���b�v�ŏ������������́A���ʂȎ��Ԃ��₷���Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ������ł���B�v�͗����ɂȂ邱�Ƃł���B
�@����ւ��ɂP�N������������B�����͂P�N���̃z�[�����[���̎��ԂŁA�Q�l�����ł���B�Q�l�̊w���̂����n�����d�����B��w�̃z�[�����[���Ȃ̂ŁA���X�����w�����݂ɂ͂����Ȃ����낤�B
�w���̂����n�����Ȃ���A�ނ炪������̋����C���[�W����B�Q�l�̊w���͎R�A�n���̏o�g�Ő��i�͑�炩�ł���B�ނ�ɂ͑�炩�̂܂܈���Ă��炢�����Ɗ���Ă���B
�@���H��ۂ�Ԃ��Ȃ��R�����ڂ̃`���C������B�R�E�S�����ڂ͂P�N���̑��`�f�U�C�����K�̎��Ƃł���B�ۑ�͏Z��̖͎ʂł��邪�A��X�T����͎ʂ�����O�ɖ͎ʂ��悤�Ƃ���}�ʂ���ɖ͌^������Ă���B
�͌^����邱�Ƃɂ�葢�`�Ƌ�Ԃ̃C���[�W���c���ł���̂ŁA�͌^������Ă���͎ʂ����Ă��炨���A�Ƃ�����|�ł���B�W�����Ē��J�ɍ���Ă���w�������邪�A�ꌩ���ĎG�ɍ���Ă���҂�����B
�ȊO�ƁA�����l���w�����Y��ɍ���Ă���B�����Ă݂�ƁA�����ł����{�Ɠ����悤�ɁA���w�Z�̍��̓n�T�~�����g�����炢���Ȃ��炵���B
���{�l�ƒ����l���w���̈Ⴂ�͐n�����g�����Ă���Ƃ������ł��Ȃ��������A�����Ɛ��_�I�ȎЉ�y�̈Ⴂ�ɂ��肻�����B
2006�N10��23���i���j
�@�I���A�������Ńf�X�N���[�N�A�������Ȃ���A���������U��Ԃ��Ă݂�ƍ����̃f�X�N���[�N�͉�������Ă����̂�����Ȃ��B
�قƂ�ǂ����ނƃ��[���̐����ł���B���܁A�w������������B��N���́g�f�b�T�������J���Ă���h�A�g�V�уN���u�̌ږ�ɂȂ��Ă���h�A�g�J�b�v���[������H�ׂ邩�炨��������h�A
�Ƃ����ׂȂ��Ƃ���ł���B�S�N���͑��Ɛv�̒��Ԕ��\�̏��������Ă��邪�A�T�v��ǂݏグ�邾���̒��Ԕ��\���l���Ă���w��������B
�S������n�܂��āA����11���A���łɂV�������߂��Ă���̂����A�G�X�L�[�X�͂܂������ƌ����Ă��������炢��������Ă��Ȃ��B�����A�l���Ă��邱�Ƃ�����Έ�C�ɐi�ނ͂������A�܂������i��ł��Ȃ��B
�Ƃ������Ƃ́A���̂V�����������̒��ɂȂ������A�Ƃ������Ƃł���B�{���͐S��吺�œ{�肽���C�����ł���B�����u���_�⑲�v�����̂̓I���ł͂Ȃ�����v�Ƃ��A�u���Ƃ���̂̓I���ł͂Ȃ�����ȁ`�I�v�ƌ����Ă��܂��B
��������ē{�炸�ɗ�Â���ۂ̂ɐ���t�ł���B�w�p�U����̉Ȋw������i�Ȍ���j�̒��ߐ�������Ă���B�[�����珑�ނ������n�߂邪�A������U��Ō��ʂ͋��I���B
���z�ӏ��⌚�z�j�W�͐�[�Z�p��T�C�G���X�W�ƈقȂ�A���n�I�ȗ̈�͂������ɗ��悤�ȗ̈�ł͂Ȃ��B
���̂悤�ȗ̈�͗\�Z�\���ɂ͋ɂ߂ĕs���ł���B�����������A�w�ҏ���������Ă���ȏ�͗\�Z�\���͋`���ł���A��U��ł��낤�Ƃ��g���C���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
2006�N10��22���i���j
�@�R���̂���Ɋ`��H�悤�Ǝv���A��̊`�������ł�����q���b�R���F�l�̓y��N�������B���X�̂��������ɂ���Ă����Ƃ̎��ŁA�S���������ӂ���B
���r���O�ł��炭���k����B�y��N�͑�茚�z�v�������ɋ߂Ă���̂łǂ����Ă����z�̘b�ɂȂ�B���z�̘b�͊y�����̂Řb���n�߂�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B
�ꎞ�Ԃقǘb������ł��A��ɂȂ����B�����v�����w������̗F�l�͗L����̂ł���B
�@�䂪�Ƃ̐H�쌓�p�̃e�[�u���̓m�[�g�^�p�\�R���A�V���A���M�A�������A����ɖ{��������ɒu���Ă���B��x�ǂ{�͖{�I�Ɏd�������ނ̂ł͂Ȃ��A���炭�e�[�u���̏�ɒu���Ă���B
�����I�ɓǂݕԂ����肷�邽�߂��B10��9���Ɂw���E�i���Љ�A�����J�̐^���x�i���їR���@���o�a�o�� \1700�j�ɂ��ď��������A�C�ɂȂ��ēǂݕԂ����v�_�͎��̂��Ƃł���B
�@��T�́u�A�����J�̋��炪��������@�|�Ȃ��A�����J�̊�b����͐�i���ōŒᐅ���ƂȂ����̂��H�v��ǂݕԂ��Ɖ䂪�����A�����J�Ɠ����������ł��邱�Ƃ�����B
�A�����J�l�̉�b�̓t�b�g�{�[���̘b�����I�Ȑg�̉�肱�Ƃ����ŁA���[���b�p�l�̊w���Ɍ��킹��Ɓu�A�����J�͔����ŁA�����I�ɒx��Ă���B���[���b�p�̊w���̓V�F�[�N�X�s�A��ǂ�Ől�Ԃ̖{���ɂ��čl�����B
�ł��r�W�l�X�X�N�[���̃A�����J�l�w���̂����A���l���V�F�[�N�X�s�A��ǂ�ł���Ǝv�����H�v�Ɩ₢�A�u�A�����J�l�̓��[���b�p�l�ɔ�ׂ�Ɨ��s���Ă��Ȃ����王�삪�����v�@
����Ɂu�l�Ԃ̉��l�ƁA���̐l�̌o�ϓI���l�͈Ⴄ�B�ł��A�����J�ł͂��ꂪ��ɂȂ��Ă���v�ƁB
����ɁA�A�����J�̌����w�Z�͎������d�A���ȂɌ�y���̍������̂������A�����������炷�X�|�[�c�≹�y�̋������}���A�Z���Ȃǂ̊�b�w�Ȃ����炳�ꂽ�B
�����āA�L���łȂ��w�͘J���ɐ�߂鎞�Ԃ����������ʼnƑ��Ƃ̎��Ԃ����Ă��A
�q���͕K�R�I�Ƀ��x���̒Ⴂ�w�Z�ɐi�܂�������Ȃ��Ȃ�A�R�~���j�e�B�[�E�J���b�W�i�E�Ƌ��璆�S�̌�����w�j�ɐi�ނ̂����������ŁA�������ւ̓��͉i���ɕ�����Ă��܂��ƁB
����͊i���Љ�̒��ŁA�T���ł͂Ȃ��w�͕K�R�I�ɐE�Ƌ���̓�����܂�������Ȃ����Ƃ������Ă���B
���{�̑�w��w�����A�V�F�[�N�X�s�A��ǂ�Ől�Ԑ����l���邱�ƂȂ����i�擾�ɔM�S�ɂȂ�X����A�A�E�������Ȃǂ�搂��Ă����w���������ƂȂǂ��l����ƁA
���{�̑命���̑�w���Z�p�擾�A���i�擾�ȂǁA�E�Ƌ��璆�S�̑�w�ւƐi��ł���ƌ��킴��Ȃ��B
�N�w���b�w����w�ڂ��Ƃ��Ȃ����S�ȓ��{�̊w���������A�����J�Ɠ����悤�ɁA�s�����͊i���Љ�̕n���w�Ɍ��������Ƃ͊m���ł���B
�A�����J�Ɠ����悤�Ȋi���Љ�ł����邱�Ƃ���҂�w�������͒m�낤�Ƃ͂��Ȃ��B
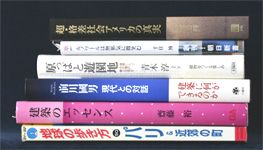
|
���A�e�[�u���ɍڂ��Ă���{
2006�N10��21���i�y�j
�@���j���̖�ɃC���^�[�l�b�g��amazon �ɐ\������ł������Ђ��͂��B�ŋ߂� amazon �Ŗ{���w�����邱�Ƃ������B
�Ƃ����̂́A�ꌾ�Ō����ƁA�����葁�����炾�B�ܔ��ߕӂ̖{���ł͍w�����悤�Ƃ���{�͂قƂ�nj�������Ȃ��B���q�A���邢��
�����֔����ɍs���ɂ��Ă���ʔ1000�~�ȏ�͂�����B����������ɏ��q�A�����֏o�������Ƃ��Ă��w�����悤�Ƃ���{������Ƃ͌���Ȃ��B
�w���������{�����܂��Ă���A��T�Ԉȓ��ɓ͂�����Aamazon �ɐ\�����ނƁA�����s�֖{�w���ɍs�����A�s�����Ǝv���Ă��邤���ɖ{���͂��̂ł���B�ŁA�����͂����{�́A
�u���m���[���͖��C�ɔ��ށ@�|�|�p�I���z�̂����߁v��Z���@�����V���i�V���� \740�j�A�u�O�욠�j�@����Ƃ̑Θb�v���G�m�@�Z�s�ЁA����ɖƉu�ɂ��Ă̐}���ł���B
�@�ŁA���������u���m���[���͖��C�ɔ��ށ@�|�|�p�I���z�̂����߁v��ǂݎn�߂�B��Z���̓j���[���[�N�ݏZ�̓��{��ƂŁA
��͉��y�Ƃ̐�Z���A���̓��@�C�I�����j�X�g�̐�Z�^���q�ŁA���e�͌o�c�H�w�̌���w�����ł���B��Z���������|�p�Ƃ́u�I���̋��т��Ă���v�Ƃ����悤�ȃ��b�Z�[�W�̔��M�ł���A
����l�A�����������l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������ƌ����Ă���B�܂��������z�������ł���B�u�I���̋��т��Ă���v�Ƃ����悤�ȁA�g�I�����l���錚�z�͂��̂悤�Ȃ��̂��h�Ƃ������悤�Ȏ����̃��b�Z�[�W�M�ł��邩�ǂ����A
�����Ă��̃��b�Z�[�W�ɑ��ďZ�ސl��K���l�ƃR�~���j�P�[�V�������ł��邩�ǂ����ł���B�I�^�N�̓O���[�v���m�Ō����������b�Z�[�W���O�Ɍ������Ĕ��M���Ă��Ȃ��Ƃ��āA�I�^�N�͌|�p�Ƃł͂Ȃ��Ƃ��Ă���B
���z���|�p����������Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����̃f�U�C���������t���Ă������Ȃ��B�܂��Ă�A�ꕔ�̐l�ԓ��m�ŕ]���������Ă��_�����ƌ����Ă���B�^�C�g���́g���m���[���͖��C�ɔ��ށh�Ƃ͌��т̐߂ŁA
���m���[���̊G�́g��������قǂ̖��C�ȍK�����ƌ��ɖ������ӂꂽ���E�h�Ƃ����m���[���l�̃G�S�Ƃ��Ắu�|�p�̂��߂̌|�p�v�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă���B�����ă��m���[���́g���ׂĂ̐l�X�̐S�����������ȕ����Ŗ������h�Ƃ��Ă���B
��Z���̌|�p�_���W�J����Ă��邪�A����͊G��|�p�����̖��ł͂Ȃ��A���z�ɂ����Ă������ł���B
���̖{�͌��z���܂߂Č|�p�̂������|�p�ƂƂ��Ă̎���������Ă���Ƃ����Ă��ǂ��B��������Ă���{�ł͂Ȃ��̂Ō��z�w�����C�y�ɓǂ߂�{�ł���B
�[���܂łɈꝄ�ɓǂݏグ��B
2006�N10��20���i���j
�@�ߑO���͎���ŏ��������Ȃ��B12:00�߂��Ɍ������ցA15:00 ��Ƃ̕�����������B�߂��ɗp���������ė���������Ƃ̎��A
���m�̒��Ȃ̂Ő��Ԙb�ɉԂ��炭�B�ƊE����ςȐ��E�ŁA�����܂��ɂ����T�o�C�o�������݂����Ȃ��̂ŁA1������Ƃ��C�������Ȃ����X���߂����Ă���Ƃ̎��B17:00 �߂��ɏI���B
����ւ��Ɋw�������k�ɂ���Ă���B�݂Ȃ��ꂼ��Y�ݎ������������B
���������w�����������̔Y�ݎ��́A�Y�o���A�F�����������Ȃ������B�݂Ȃ��̂悤�ȔY�݂��o�����đ�l�ɂȂ����̂����A�ŋ߂͐F�������̔Y�݂͂قƂ�Ǖ����Ȃ��B
���̔w�i�͎�҂�������l�ɗ�����A�Ƃ�������r�����Ă��Ƃ��l������B���z���u���A�Ƃ������ƁA�l�ɗ����A�l��������A�Ƃ������Ƃ͎��Ɍ��킹��Ɠ���ɒu����B
�l�ɗ����A�l��������A�Ƃ�������⊴�����L���łȂ��ƁA�l�ɑi�������A�����Đl�Ɋ�����^����悤�Ȍ��z��v���邱�Ƃ͕s�\���Ǝ��͍l���Ă���B
�b�����ɖ߂����A��҂����̋ꂵ�݂�Y�݂͈ȑO�Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă���B�Y�ݑ�����҂����ɂ͎����̐l���o����b���Ă�邵���Ȃ��B
�����̐l���o�����Y��ł����҂Ɋ�����^���邱�Ƃ��ł��Ȃ�����t�͎��i�ł���Ƃ�������B
�̖̂V��͈�������F��Ȍo������������A�o�Ƃ��ĖV��ɂȂ����̂����A�����玩���̌o���������Đl��@�����Ƃ��ł����̂ł���B
�{���͂����^�ʖڂȋ��t�̑��݂Ȃ�č݂蓾�Ȃ��b�ł���B�w����E�C�t���đ���o���B
�@�w�����A��ƁA�܂��ʂ̊w���������A���x�͌��z�v�Ɋւ���b�ł���B�{���͐F��ȘA���ƐF��Ȍ��z�̘b�����Ă��鎞�͎��Ɋy�����̂ł���B
���x�͂R�N���̊w���ƓǏ�����v�悵�悤���ȁE�E�E�E�@20:00 �߂��ɏI��
2006�N10��19���i�j
�@�ŋ߁A�����l���w���Ƙb������@�����B�����Ƃ����̕����������Ƃ��������A�ނ���F��Ȃ��Ƃɓ����Ă����B���{�ł͍l�����Ȃ������Љ���L�̃R�l�N�V�����ɂ͋�������邪�A
�ނ�͓��{�ł��R�l�N�V�����łǂ��ɂ��Ȃ�A�Ƃ������������Ă���B���Ƃ��A������No.1�̖k����w�̓��w�����ɂ����Ă��邱�Ƃ��A�Ⴆ�Γ�����w�Ȃǂ̓��{�ł��O���C�h�̍�����w�̓��w�����ɂ����Ă������Љ�Ɠ������Ƃ�����A�ƌ��Ă���_�ł���B
�����Љ�ł���悤�Șb�͓��{�ł͌����č݂蓾�Ȃ����Ƃł��邪�A�ނ�ɂƂ��Ă͐M�����������ł��낤�B
�����Љ���i���Љ��R�Ƃ��đ��݂��邪�A���{�Љ�͕����Љ�ł���A�ƌ����������A���{�Љ�ł��ڂɌ����Ȃ��i���Љ���݂��Ă��邱�Ƃ��B
�i���Љ�͎����ɔ��f�����̂���ʓI�ł���B
��T�Ɍ����Ȃ����A�Ⴆ�A�e��1500���~�̔N��������Ƃ���̎q���͔N��1500���~�������悤�Ȋ�Ƃ֏A�E����P�[�X�������B�t�ɁA�N��600���~�鏊�̎q���͔N��600���~�̊�Ƃ֏A�E�����Ƃ������悤�Ɏv����B
�N��600���~�̏��́A�N��1500���~���҂��ƒ���̎��Ԃ�m��Ȃ��̂ł���B
�Ƒ��̐����̒��Œm�炸�m�炸�̂����ɁA����������������̃��x���̒��Ŏ����̐������ɓK���Ă���A�E���I�����Ă���̂ł���B
���ꂪ�ڂɌ����Ȃ��i���Љ�̈�[�ł���A�����ɕ����I�L�����Ƃ��Ă̊i��������Ă��邱�Ƃł���B�����ȓz�͂��̂悤�Ȋi����F�����Đe�Ƃ͈�������̂�g�ɕt���ď�̃����N�Ő������悤�Ƃ���B
������A�����邱�Ƃɂ���ď�̃N���X���������Ƃ����̂ł���B�܂��A
�L������g�ɕt���邱�ƂŁA��̐��������N�Ő����悤�Ƃ����B�����A�����ȎЉ�ł���Ɗ��Ⴂ���āA���s���R�Ȃ�����Ă����҂����͊i���Љ�̑��݂ɂ��C���t�����A�܂��L������g�ɂ��悤�Ƃ͂��Ȃ��Ő����Ă���̂ł���B
�t�ɁA�L������g�ɕt���鎖�������A���ۂ���҂�����B
�@�����l���w�������͋Z�p��g�ɕt�������Ƃ̊�]������悤���B���ɒ����l���w�������͑��ƌ�����R�N���̌������I�тł��G���W�j�A�����O�n��I������҂��命���ł��邱�Ƃ͑���w�ł������ł���B
�����Ƃ��A�����Љ�͐������ł��邩��Z�p�҂̗{�����}���Ƃ��Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�����A���{�Љ�ł����x�������ɂ����Ă͋Z�p�̌��オ��s�������A�₪�ċZ�p�ݏo���́A���Ȃ킿�n�����̏d�v�����������悤�ɂȂ����B
�{���ɏd�v�Ȃ��Ƃ͑n������g�ɕt���邱�ƂŁA�n�����͖L�����̏�ɑ��݂��邱�Ƃł���B�L�������������Ă��Ă͑n�����͐g�ɕt���Ȃ��̂ł���B�L�����Ƒn������g�ɕt����ƁA�ǂ̂悤�ȎЉ�ł�����ł���̂ł���B
�h�C�c�ł̓}�C�X�^�[�ւ̓�����ގ҂Ƒ�w�i�ގ҂͖��m�ɕ������Ƃ����B�����ł����{�̒��H��Ɠ����悤�ȃ}�C�X�^�[�̈琬�ɗ͂𒍂��ł���B���{�̃}�C�X�^�[�͒��H�ꂪ�������Ă���悤�ɁA���ł̊�@�ɂ���B
���z�̕���ł��n���͂��v�������ӏ��n�Ƃ�����T�|�[�g����G���W�j�A�����O�n������B�n���̑�w�ł͍ŋ߁A�ӏ��n��I������w�������X�Ɍ������A�t�ɃG���W�j�A�����O�n��I������w���������Ȃ��Ă���X��������B
�G���W�j�A�����O�n��I������w���ɂƂ��Ă��n�����͕K�v�ł��邪�A�����͑n���������ۂ��邪�̂ɃG���W�j�A�����O�n��I�����Ă���X��������B
�������A������w�ł͈ӏ��n�ɐi�ގ҂����|�I�ɑ����Ƃ����B���̌��ۂ��������A���{�̎�҂͊i���Љ�̒��ŏZ�ݕ������s���A�L�����̗L���ɂ�鎩�R�I���̓���I�����Ă���悤�ł�����B���̂悤�Ȍ��ۂ⒆���l���w���̓���������ƁA���{�Љ�͒����Љ�̌���Ɠ����悤�ȎЉ�Ɍ�߂肵�Ă���悤�ɂ��v����B
�m���ɓ��{�Љ�͋t�s���Ă���A���z�̕���ł͑n�����闧��̐l�ԁA�����A���z�ݏo���l�ԂƁA���݂�S���l�Ԃ̃A���o�����X���ۂ��}���悤�Ƃ��Ă���B����͌��z�E�\�ɂ����鋳��@�ւ̓�������̊�@�Ƃ�������B���z�̏����͈É_���������߂Ă���ƌ�����B���ꂩ���̎Љ�͋Z�p�҂�����قǑ����K�v�Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł���B
�₪�āA���{�ƒ������t�]���鎞������ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz������A���{�Љ�̋��͐i�݁A�i���͊m���ɍL�����Ă���B
2006�N10��18���i���j
�@10:50 ���瑲�ƌ����̒��Ԕ��\���n�܂�B���͌ߑO���̒S����12:10�܂Ŏi����s���B�����͑��ƌ��������̔��\�ŁA���T�͑��Ɛv�̔��\�ł���B
���ƌ�����I�����Ă���w���������������A�Q�����ڂƂR�����ڂ̂Q�R�}�̎��Ԃ�����U���Ă���B
����̊w���͒�����������I�����Ă��邪�A���ɂ́A�P�O�����Ƃ����̂ɒ���������������I�����Ă��Ȃ��w��������B���_�̓��e�ł��邪�A���炩�ɕs���̓��e������A�_�̐ݒ肪���������H�Ǝv������̂�����B
���ƌ����͊w�����Ǝ��ɂł�����̂ł͂Ȃ��B�{�l���g�ł�����h�ƌ����Ă��A�ł������������e�͍��Z���̌������\���x�̂��̂ł����Ȃ��B
�܂��A���ƌ��������t�̎w���ɂ����̂ł����Ă��A���̓��e���w��ŕ]�������悤�ȓ��e�ł���Ƃ͌���Ȃ��B�w���̑��ƌ����́A���鎞�́A���t���l��������I�i���ݓI�j�ȓ��e�ł���ꍇ������B
�����I�i���ݓI�j�Ȃ��̂��w���ɂ�点�ăg���ł��Ȃ��A�ƌ����y�����邩�̂���Ȃ����A���Ђɏ�����Ă�����e��A�w��̘_�����ł��łɖ��炩�ɂ���Ă��鎖���Ăэs�����Ȃǂ܂������Ӗ����Ȃ��̂ł���B
�őO���̌����Ƃ͎��s����̒��ōs���A�܂������҂̓��̒��Ŗ͍�����Ă�����̂ł���A����͉����I�Ȏ��݂ł����Ȃ��B
�w�����s���Ă��鑲�ƌ����͌����̊�b�I�ȈӖ�������A�܂��A�w�����鋳�t�������s���A����ژ_��ł���̂������_�Ԍ�����̂ł���B
�őO���I�ȃe�[�}���s���Ă��邩�瑲�ƌ������s�����l������̂ł���B����͑��ƌ��������ł͂Ȃ��A���ƌ����ł��������Ƃ�������̂ł���B
���̂悤�ȈӖ��ł͎w�������̗͗ʂ�����Ă���A�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�w�������͋��t�̑㗝�I������S���Ă��Ƃ����m���Ă��Ȃ��w���������Ǝv����B
�@15:00 ���狳����A��w�@�����Ȉψ���@16:15 �߂��ɏI���@���̌�A17:00 ��������W�̉�c���s����B���t�����������|�[�g��ǂތ���A���t�͌�������ȊO�̎d���ɂ��Ă͐ӔC�̏��݂��ł��邱�Ƃ��v���m�炳���B20:40 �ɏI��
2006�N10��17���i�j
�@9:10 �����w�@�̍u�`�ł���B����A�}篍u�`�����������Ă����̂ŏ����͂��Ă��Ȃ��B�Ƃ肠�����A�{��ǂ�Ń��|�[�g�������Ă��炤���Ƃɂ����B
�u���z�̃G�b�Z���X�v�i�֓��T���@A.D.A.EDITA�o�Łj��ǂ�ł��炤���ɂ����B�`���I���z����߁E���㌚�z�܂ŁA��Ԙ_�A�ӏ��_�܂��ď�����Ă���B
�G���W�j�A�n�̉@���ɂ͓K�ނ�������Ȃ��B���z�Ƃ̍֓��T����͌��I�ȕ����ƕ����B�܂��{�ɍڂ��Ă���ʐ^�͑S�������ŎB�e�������̂��g���Ă���炵���B
������A������Ă�����e�͎����̌��t�ŏ����ꂽ���̂ł���A�����͂̂��镶�͂Ɠ��e�ɂȂ��Ă���B���̂悤�ȈӖ��Łu���z�̃G�b�Z���X�v�͗ǂ��{�ŁA
���N�A�}���قɓ���Ă�����Ă����{�ł���B������Ă��邱�Ƃ������ł���Α債�����̂ł���B�ǂ����|�[�g����o����邱�Ƃ����҂��悤�B������@��Ɏ���������x�ǂݒ����Ă݂悤�B
�@�R�E�S�����ڂ͂P�N���̑��`�f�U�C���U�̉��K�ł���B�Z��̖͌^����ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��B�}�ʂ̃R�s�[���n�߂�O�ɁA�}�ʂ����Ē��Ր}�̃X�P�b�`�������A
����ɐ}�ʂ����Ȃ���͌^�����A���̌�Ő}�ʂ̃R�s�[�����邱�Ƃɂ��Ă���B�͌^���ŋC�Â������Ƃ́A��^�̃J�b�^�[�i�C�t���g���Ă���w�������邱�Ƃł���B
�����߂̃J�b�^�[����Ȃ��ƃX�`�����{�[�h���Y��ɐ�Ȃ��B�܂��A�������J�b�^�[���g���Ă���w���͏��܂߂Ƀi�C�t�̐��܂낤�Ƃ��Ȃ����Ƃł���B
�X�`�����{�[�h���S�T���ɐ�Ƃ����ӂ��Q�`�R������B��Ƃ����Ȃ��玞�X�w�������Ƙb���̂����A�w���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̎��Ԃł�����B16:20 ���ƏI��
2006�N10��16���i���j
�@�ߑO���͔�}�{�Ҋm�F���ނ������֒�o���邽�߂ɓ����s������̋�����֏��ޑ��t�̐\���肢�ƁA�r�U�����\���̂��ߒ���s�����ːЏ��{���t�̐\�������邽�߂ɗX�Ǎs���B
�ϔC�����������A�\��������������A�בւ�����A�ȂǂŌ��\��ςł���B�w���̐e�����������q���̂��߂ɕ�������킸��������Ă���̂ł���B�e�̋�J�A�q�͒m�炸�ŁA�V�ѕ����Ă���w���������̂��낤�B
�@14:00 ���牪�_���̓s�s�v��R�c��ł���B�c��͗p�r�n��̕ύX���ł���B�p�r�n��̕ύX�͔F�߂��A15:30 ���I���B
16:00 �߂��Ɍ��������@���[���`�F�b�N�����邪�A�V�O���ȏ�͖��f���[���ŁA��ЂƂ̃��[�����m�F���ăS�~���Ɉڂ��̂���ςł���B�؍����R��w�̗��搶���烁�[���������Ă���B
���������Ř_���������̂����A�p���Ń��[��������肵�Ă��邪�A�����ŏ�����킯�ł͂Ȃ��B���搶�Ɛ������肵�A���ɕԐM���[���𐔖{�������A�C���t����18:00 ���߂��Ă���B
�@��������瑲�ƌ����̒��Ԕ��\������̂łS�N���͏����͑O�����ł���Ă���B�����A�S�N���ő��Ɗ�]�̊w���͒��Ԕ��\�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂����A�܂������o�Ă��Ȃ��w��������B
�����Q�O���߂��Ă���̂����A���_�N��͂Q�O�Έȉ��ł��낤�A���̏؋��Ɏ����̎��Ȃ̂Ɏ����̂��Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B���������̂ł���B
���̐��T�ԁA�������ɗ��Ă���w���������A���Ԕ��\���I�������A���̗������玩�ȓs���̒����x�ɂɓ���̂��낤�B���̂悤�Ȃ��Ƃ͂���ׂ����ł͂Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ��B�R���X�^���g�ɑ����Ă����邩�ۂ�����l�Ƃ��Ă̎w�W�ł���B
�@
2006�N10��14���i�y�j
�@�v���U��̓y�j�x���ł���B���q�̗����p���Ōg�ѓd�b�����ƃ��[�����Ă��Ă���̂ň�x�͓d�b���Ă݂Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
7:30 �A�p���ł�23:30 �ł���B�d�b������̂ɗǂ����Ԃł���B���������d�b�����Ƃ��댳�C�̗ǂ��Ԏ����Ԃ��Ă����B
���{�l�قƌĂ�闾�ɓ����Ă���Ƃ������ƂŁA�p���s���Ŋw�ԓ�����w�̐�y��y���w�Ԃ��߂ɗ��w���Ă��鑼�̓��{�l���w���������������ɓ����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�Q���̎ʐ^�͂���ƃ}���T�[�h�����̂R�K�Ɏ����̕���������悤�ɂ݂���B
���E���B���b�g���z��w( Ecole d'architecture de Paris La Villette )�̘b�͕����Ȃ��������A
�����w�F��p���W�F���k�̏����Ƃ͒m�荇���Ă��Ȃ��炵���B�p���W�F���k�̏����ƗF�l�ɂȂ�̂́A���q�̗����e�Ɏ��ăV���C�Ȃ̂ł��Ȃ������낤�B�P�O���قǘb�������B
�d�b�������A���[���ŗ��̎ʐ^�������Ă����B��w���͊فi�₩���j�A���邢�͂���̂悤�Ɍ�����B���̂���ꏊ�̓��E�R���r���W�F�v�̃X�C�X�ق�u���W���ق�����g���ۑ�w�s�s�h�̒����������B
���́g���ۑ�w�s�s�h�͂S�N�O�Ƀp����K�ꂽ���ɃX�C�X�ق�u���W���ق����w���邽�߂ɖK�ꂽ���Ƃ����邪�A�Â��ȍL��ȕ~�n�ł���B
��͒����̂ŐF��ȏ���m�点�Ă���邾�낤�B
�@�����s���p�ق��u���a�P�O�O�N �O�욠�j���z�W�v���P�P���T���i���j�܂ŊJ�Â���Ă���B�O�욠�j�̓��E�R���r���W�F�̎������ŋΖ����Ă������Ƃ�����A�܂��O�����O�͑O�욠�j�̎������ŏC�s���Ă����������������B
�O�����O�ƕ��сA���{�̋ߑ㌚�z��z�������z�Ƃł���B�����w������ɓ������̐X�́u����������فv�����w�ɍs�������Ƃ�����B���Ԃ�����Ύ����s���Ă݂悤�B

|

|
�p���g���ۑ�w�s�s�h���̗�
2006�N10��13���i���j
�@�ߑO���A����ŊJ�c����̘_���̃`�F�b�N�@�R���Ԃ��܂�̎��Ԃ��₷�B�������Ɍ������������B�������ŗX�֕��⏑�ނ̐��������Ă�����J�c�������@ 14:30 �ɂȂ��Ă����B���炭���Ԙb�����āA�_���ɂ��Ă̋c�_���킹��B
�_�����̂P �̒��ŋL���s���m�ȂQ�Җڂ̘_�_���������炩�ɂȂ����B���_������グ�ĕs���ȕ����𖾂炩�ɂ��A����ƑS�e�����炩�ɂȂ����B���Ƃ͎��M���̌��e�����������邾���ł���B�ǂ��_���Ɏd�オ�邱�Ƃ����҂������B
17:30 �I���@�Ԕ�����ꂸ�ɋ��c���邽�߂Ɋw����W�W�̎����������ĕ�W�`�[���̃`�[�t�̕����������B���̌�A���������������ċc�_������B�����쐬���������͖v�ƂȂ邪�A���߂ċc�_�����헪�ŗՂނ��ƂɂȂ����B19:30 �I���A�������֖߂�B
�@JIA �̃��[�N�V���b�v�̉ۑ�Ɋւ��鎑���ƃr�f�I�e�[�v���؍��֑��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�r�f�I�e�[�v�Ǝ���������ėX���̏����𐮂���B
������ǂ֓d�b����ƁA�X�֕��͂Q�S���Ԏt���Ă���A�Ƃ����̂ŗX�����鍫��������Ĕ�����ǂ������B20:30 ���ۗX��EMS �̎葱�����I����B���T�̏��߂ɂ͊؍��֓������邾�낤�B21:00 �O�Ɏ���A�Ȃ�ƂȂ��Q�������ł������B
2006�N10��12���i�j
�@���N���āA���[�����`�F�b�N����Ƒ��q�̗����烁�[���������Ă���B�����Ă��邱�Ƃ͘A����Ƌ��̂��Ƃł���B�����B���b�g���z��w�ł̊w�������◾�ɂ��Ă͉���������Ă��Ȃ��B
�A�w�r�U���擾���Ă������ɂ�������炸�A�p���ł̑؍������擾���Ȃ��Ƃ����Ȃ���������Ȃ��A�����Ă���B�t�����X���A�t���J����̈ږ���A�J���ȂǂŃf���P�[�g�ɂȂ��Ă���̂��낤�B
�S�N�O�Ƀp���ɍs�������A�V�������E�h�E�S�[����`�œ��{�l�V�����t���[�p�X�Œʂ����t�����X���NJ����̐��Ȍv�炢���v���o�����B
�@9:30 ������o�đ�w�������B�Ԃ̃R���\�[���{�b�N�X�̂b�c�@������Ɖ��Ă��������v���t���Ă���B
���C�Ȃ��b�c�@�̃��W�F�N�g�{�^���������ƍ��܂ŏo�Ă��Ȃ������b�c���o�Ă���ł͂Ȃ����I�@
���݂ɂb�c�̍Đ��{�^���������Ɠ����Ȃ������b�c�̉��y�������B�b�c�@�ɓ������܂܂̃t�B���b�p�E�W�����_�[�m�̉��y���ԓ��ɗ����B
���Ă����̂ŏC���ɏo�����Ǝv���Ă����̂����A���̂܂ɂ��̏Ⴊ�����Ă���B�����������܂ė������Ȃ��������łh�b�����ɖ߂����̂��낤���H�@�������A����ԓ��ʼn��y��������B
�@10:50 ������{���z�j�̍u�`�A�w�������ɓV���T�b�V�Ȃǂ����Ă��炢�Ȃ���A�[�܂�ɂ��āA���ƋZ�p�ɂĘb������B�w���B�͂܂��ċx�C���������Ȃ��̂��W�����Ă��Ȃ��B�ނ�͈�N�������������Ƌx�݂̉������ɂ���̂��B
�k���N����j���e���ڂ̃��b�P�b�g�����ł������Ȃ������Ȃ̂ɕ��a�{�P�A�V�R�{�P�̎�ҒB�ł���B�������A�M�S�ɏ��܂߂Ƀm�[�g������Ă���w��������������̂ł���B
�ߌ�͐v���}�̎w���ɔ��u�t�̐搶�������邪�A���ƏI����A�v���U��ɔ��̐搶�ƌ��z�_�����킵���B
���̐搶���������̊w���̓����ɂ͐S�z���Ă�����B�w�������ɂƂ��āA�{���ɕ������A�������������g�Ƃ��Ċ���ł���ł��낤�B
2006�N10��11���i���j
�@10:00 ���_�����݉ۂ̉ے�����ȉ��R��������A�ے����ړ��ŕς�������Ƃɂ��䈥�A�ƁA���T�̓s�s�v��R�c��̑ł����킹�����˂Ă̘b�������̂��߂ł���B
�ł����킹�I����̉w��n��̊J���ɂ��Ă̘b�ɔM�����̂��������B�Z��p�̍H��U�v�A�H�i�W�̒c�n�A�^�A�W�̒c�n�ȂǁA�F��ȈĂ��o�����������A���������ď����W��g�D�̌��Ē����œ��������Ȃ����낤�B
11:30 �I��
�@���̌�A�Ԃɏ���ēo�Z���悤�Ƃ������A�G���W����������Ȃ��B�Z�����[�^�[�������Ȃ��̂ł���B�}���ŁA�Ƃ����Ă����Ԃ͂����邪�[�d��ŏ[�d���邵���Ȃ��B
��1���Ԕ��[�d���G���W�������������A���x�̓G���W�������������B�ŁA�����́H�@����͊�1���Ԃ����Ă��Ȃ��B
�������A�킸��1���ł����Ă��o�b�e���[�����d���Ă��܂����Ƃ�����A�o�b�e���[�̎����ł��낤�B�Ԃ��w�����ĂS�N���߂��Ă���̂Ńo�b�e���[�͂S�N���o�߂��Ă���B�����̎����͂Ƃ����ɉ߂��Ă���B���̂܂܂ł͍��N�̓~�܂ł����Ȃ����낤�B
�@16:30 ���狳����c�@������R�c�����������B18:00 ���狳���̈��݉�ł��邪�A�I�������̂�19:00 �O�A�o�Ȃ���\��ł��������̒����v�킵���Ȃ��̂ŋ}篌��Ȃ����Ă��炤���Ƃɂ����B
�P�͏o�Ȃ��Ȃ������A�ڂ��g�����Ƃ��Ă���̂ł���B����M������Ƃ݂Ă悢���낤�B��N�̓�̕��͓��݂����Ȃ��B
2006�N10��10���i�j
�@�����͓d�Ԃɂēo�Z����B�v���U��ɐܔ��w�����w�܂œk���ʼn��������B�̒��͊��S�ł͂Ȃ����̗͂Â�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�G�߂��ǂ��̂ŏT�Q��͓d�Ԓʋ��������B
�@�R�E�S�����ڂ��P�N���̑��`�f�U�C�����K�̎��Ƃł���B�Z��̖͌^����ł��邪�A�}�ʂ̌����A�g���ĂȂǓ����g��Ȃ��Ă͖͌^�͂ł��Ȃ��B�w�������ɂ͋ꂵ��łق����̂ł���B
�������Ȃ��Ǝ|���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���ƏI����A��W�W�̃~�[�e�B���O���s�������A�~�[�e�B���O�̍Œ��ɏĂ����̏L�����Y���Ă���B��w�̍Z�ɓ����Ă����̏L���ɏ[������Ă���B
�ȑO��������������������^���Ă������A�ŋ߂ł͌������ŋ����Ă��悤�Ȗʔ����w���͂��Ȃ��Ȃ����B�l���Ă݂�ƁA�ȑO�̓n�[��ނ�ɍs���Č������œV�Ղ���������A�����Ă����肵�Ă����B�~��̂��ǂ�A���͓���I�ɍ���Ă����B
�ŋ߂͌������ŋ����Ă�����A�������ނ悤�Ȋw���͂��Ȃ��Ȃ����B�w�������Ƃ��I���Ƃ����ɃA�p�[�g�A�肽�����Č������ɋ����Ȃ��Ȃ����B�܂��Ă�A����������������݂ɍs���Ă܂��������ɖ߂��Ă���悤�ȗE�܂����w���͂��Ȃ��B
����ɂ��Ă��A�Z�ɓ��S�̂��Ă����̏L���ɔƂ���Ă���͖̂��ł���B����œx���߂���B
2006�N10��9���i���j
�@����͉䂪�Ƃ̔��ň����@��B�����A�@�������͑S�Ē��ɐH���Ă���B�����͐F�X�l�����邪�A���̋��ɐA�����싞�n�[�̖��傫���Ȃ肷�������Ƃ��l������B
�싞�n�[�͂U���̍������A�傫���}���L���Ă���B���ɂƂĉď�ɑ��z������K�v�Ƃ��鎞�ɓ싞�n�[�̎}��t���e�������Ă���B���������Ĉ��̐��炪�����̂ł���B
�܂��A���̏��ł���x���s���Ă��Ȃ��̂������ł��낤�B����ɁA�A���Ă�����̎�ނ��u������v�ŊÂ���ނ̈��ł���B���������Z�Ŕ��̎���ꂪ�܂������ł��Ȃ��B
��������H���̂ɏ����������Ă���̂ł���B���N�����́A�싞�n�[�̑I��Ŏ}�����Ȃ����ėz��������悤�ɂ��A���̎��������܂߂ɂ������B
�@���̘A�x�Łw���E�i���Љ�A�����J�̐^���x�i���їR���@���o�a�o�Ёj��ǂށB���������w������ł������R�O���N�O�ɂ́u�a�߂�A�����J�Љ�v���Љ��A�P�O�N�����Ȃ������ɓ��{���A�����J�Љ�Ɠ����悤�ȕa�߂�Љ�ɂȂ�A�ƌx�����ꂽ�B
�g�a�߂�Љ�h�Ƃ́A���̓��{�̎�҂����̂悤�ɁA�s����̖�����҂̑��݂Ǝ��Ԃ��̂��̂ł���B
�\�z�����x��͂������A���ꂩ��Q�O���N��A���{���A�����J�Љ�Ɠ����悤�ȕa�߂�Љ�ɂȂ��Ă��܂����B�w���E�i���Љ�A�����J�̐^���x�͂R�O���N�O�̕a�߂�A�����J�Љ�A���̌�A�ǂ̂悤�ȎЉ�ɕω����������L���Ă���B
����́A����Ӗ��ł́A���{�Љ���ꂩ��ǂ̂悤�ɕς���Ă����̂���\�����Ă���ƌ�����B���҂̓A�����J�Љ���u�����K���v�A�u�v���t�F�V���i���K���v�A�u�n���K���v�A�u�������ڂ�v����Ȃ�Ƃ��A
�u�����K���v�Ɓu�v���t�F�V���i���K���v���S�̂̂T�������ŁA�u�n���K���v�Ɓu�������ڂ�v���X�T���ł���Ƃ��Ă���B
�A�����J�̒��Y�K���ƌ���ꂽ�l�X�͈ꕔ���u�v���t�F�V���i���K���v�ɁA�命�����u�n���K���v�ɂ������ڂ�Ă��܂����A�Ƃ��Ă���B�u���Y�K���v�Ƃ���Ă����l�X���u�n���K���v�ɂȂ�̂ł���B
���ɕ|���Љ�������邱���\������邪�A�w���E�i���Љ�A�����J�̐^���x�ɏ�����Ă��邱�Ƃ́A�m���ɓ��{�Љ�ɔ��f����A���{�Љ�Ɋi���Љ�������邱�Ƃ�\�����Ă���̂ł���B
�@�����O�̒����V���̓������ɍH�ƍ��Z�̐搶�̓������ڂ��Ă����B����ɂ��ƁA���E�Ƃ��Ă̍H�ƍ��Z�ւ̋��l�͑������A�H�Ƃ̐�勳����s���H�ƍ��Z�͑������Z�ɕς��A�]���̐�勳�炩�痣��A�������e����w�ɂ�낤�Ƃ��鐢���ł��邱�Ƃ�������Ă����B
����H�Ƃ̌���Ŏx����ׂ��l�ނ������s�ɂȂ����Љ�ł�����B���{�̋���Ɛl�ދ����̎��ԁA����Ɂw���E�i���Љ�A�����J�̐^���x�ɏ�����Ă��邱�ƂȂǂ��l�����킹��ƁA
���{�ł��A�����J�Љ�Ɠ����悤�ɁA��w�𑲋Ƃ��������ӎ����������命���̐l�X�ł��X�T���́u�n���K���v�Ɓu�������ڂ�v�K���ɑ�����A�Ƃ������Ƃ��e�Ղɗ\�������B
�@�T���Q�S����Diary �Łu�����Љ�v�i�O�Y�W���@�����АV���� 780�~ �j���Љ���B���́u�����Љ�v�ɏ�����Ă��邱�ƂƁA�w���E�i���Љ�A�����J�̐^���x�ɏ�����Ă��邱�͍��͓����ł���B
�����̖{�́A���������A�Љ���g�ɕt�����A�D���Ȃ��Ƃ����āA�D���Ȃ悤�ɐ����Ă���w�������̏����Ɍx����炵�Ă���Ɠǂݎ���B
2006�N10��7���i�y�j
�@�{���Ȃ�A10:00 ����k��B�s�������w�ɂŃV�j�A�J���b�W�̍u�`�̗\��ł��������A�̒����������ƂŁA�s�E���̕����C�𗘂����Ă��������ĉ����ɂȂ����̂ł���B
�̒��͎���M�C���ň����B���̂܂܍u�`���Ă����Ƃ��Ă���u���ɂƂ��Ė�������������̂ł͂Ȃ��������낤�B�̒����S�ōu�`���������B�������X�b�L������Ȃ��̂����̕��ׂł���B�C�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�@15:00 ����k��B�s�����p�قłi�h�`�i���z�Ƌ���j��ẪZ�~�i�[�ł���B�؍��`�[������������W�ŐӔC���ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ő̒��������Ă��o�Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Z�~�i�[�͍��N�̂i�h�`�V�l�܂̐��R�I���̍u���ŁA�I���ハ�[�N�V���b�v�̉ۑ蔭�\������B
�����͎���̂S��i���Љ�Ȃ���v�ƃf�U�C���|���V�[�ɂďq�ׂ�ꂽ�B�I����A���p�ق̃��X�g�����Ńp�[�e�B�[������A���[�N�V���b�v�ɎQ������e��w�̃`�[���̈��A���������B�{�w����������������̂T�l�����A�����B
1���ԂقǂŏI�����A�ꏊ���i�`�z�e���Ɉڂ��ĂQ����J���ꂽ�B�����Ƙb���@����������A�������Ԃ������ċc�_�����ɂ͂����Ȃ��B�����͊O�ς��ӎ�����Ă���悤�Ɍ����邪�A���͓������ׂ����A���Ԃ������ăv�������l�߂��Ă���B
�������ӂ��߂āA�����a���ȂǏ������z�Ƃ̊��V���������������N�����Ă���B�ŋ߂̌��z�E�ł́A�P�O�N�O�̌��z�̒������E�p���ĐV�����������Q�����Ă���̂�������B�w�����N�Ɍ����邱�Ƃ́A�����a���ȂǁA�ŋ߂̌��z�Ƃ̍�i���������Ă݂鉿�l�͂���B21:30 �I��

|
�Z�~�i�[�I����A���z�Ƃ̐��R�I��(����)�Ɗw������
2006�N10��6���i���j
�@�閾���O�A���������Ėڂ��o�߂��B�ߏ��̖ؑ��Z��͂����ƃK�^�K�^�A���������h��Ă���ɂ������Ȃ��B4:00 �߂�����5:00 ���܂Ńe���r���݂Ȃ���E�g�E�g����B
�����͍u�`���Ȃ��̂ŋv���U��ɂ������߂����B�ߑO�����������߂����͈̂ꌎ�Ԃ肭�炢���낤���B�̒��͂܂��S���ł͂Ȃ��B��ꂪ���܂��Ă����̂��낤�B
������o�Z�����܂������ނ����B�x���Ƃ����T���߂ɂ͏o�������B�����͉Ȍ���\���̏��ލ쐬���T���Ă���B�����̒��𐮂������B
�@�R�N���������A�����̃Z�~�i�[�s���̑ł����킹�ł���B�G�k�̒��Ŋ�����������̂́A���z�̏��������łɓ�������̒����ɂ��邱�Ƃł���B���z�m�⌚�z�Ƃ���Ă�ׂ�����@�ւł����w�ɂ����āA�w�����\�����̂Ă悤�Ƃ��Ă���B
���̔w�i�́A������ׂ��f�U�C���W�̉Ȗڂ�������ׂ��ł��邪�A�G���W�j�A�����O�Ɋւ���Ȗڂ����܂�ɂ����߂��邱�Ƃ��A�F��ȈӖ��Ō��z�̏������Ă���悤�Ɏv����B
���������w������ł��������̃J���L�������Ɣ�ׂĂ݂Ă��A���̕����͂邩�ɊJ�u�Ȗڂ͑������A�������G���W�j�A�����O�n�̉Ȗڂ������Ȃ��Ă���̂ł���B���z�w�Ȃ̃J���L�������̒��ɐF��ȉȖڂ����Ă��܂��̂͂��͂���E�ƌ����悤�B
�{���̌��z�w�Ȃ̃J���L���������猚�z�H�w�Ȃ̃J���L�������ɋ߂Â��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H���������A���{�I�Ƀf�U�C���̃R�[�X�ƃG���W�j�A�����O�̃R�[�X�̋���Ȗڂ��������ǂ��̂�������Ȃ��B
������ɂ���A���̂܂܂ł͒��r���[�ȍ\���ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�����͋v���U��ɎႢ�A�[�L�e�N�g�̘b��������A�y���݂ł���B
2006�N10��5���i�j
�@�Q�����ڂ͓��{���z�j�̎��Ƃł���B��t���ɂ��Ẵr�f�I���ςĂ��炤�B������F�i���������ڂ��j�̍������X�N���[���ɉf���������B
�����͑S�ċȐ��ō\������Ă���B�ꖡ�̗ǂ��s���Ȑ��A�ɂ��_�炩�ȋȐ��A�c��݂���������悤�Ɍ�����Ȑ��A�l�X�ȋȐ��ɂ���đS�̂��\������Ă���B
���z�f�U�C���ɉ��p�ł������ł���A����A���p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�������F��Ȋw������������B���������A�������̓I�Ɍ��������鏀�����w���̎d���ł���B�Ƃ��낪�A���n���A�������ꂽ���̎���A���͌�����Ȃ����A���Ƃ����������Ƃ��Ă��������ւ̓����͒������B
���̎������ς����A�Q�O�N��̎���͂����Ƒ�ςȎ���ɂȂ肻�����B�m���Ɉ��������݂��߂Đ����邵���Ȃ��B1���A1�����[���������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@��������m�g�j�|�a�r�Ŋ؍��h���}�A�����E�\�N�z���o�́u�t�̃����c�v���n�܂�B�����E�\�N�z���o�́u�~�̃\�i�^�v�A�u�H�̓��b�v�ɑ����t�ďH�~�V���[�Y�ł���B
�I�[�v�j���O���������A�؍������z�Ƃ������I�ȃX�e�[�^�X���_�Ԍ�����B�����E�\�N�z���o�̃h���}�ɂ͊؍��l�̖��A�X�e�[�^�X�A�ȂǐF��Ȃ��̂����o����Ă���B�L���X�e�B���O�͓��{�l���ӎ����Ă���悤�ɂ�������B
���̃h���}���ŏI��܂Ŗ��T���邱�ƂɂȂ�̂��낤���H�h���}�̓W�J���y���݂ł���B
2006�N10��4���i���j
�@���A���[�������ɓ����ăj���j�N�������Ղ���������Y�q�����[������H�ׂ��B���̂������A�����͊P���~�܂��Ă���B�Ƃ͌����A���S�Ɏ~�܂����킯�ł͂Ȃ��A���܁A�˔��I�ɊP�͏o��B�˔��I�ɏo��̂ŁA�b���I�ł�����B
�@�Q�����ڂ��R�N���̌��z���[�~�̎��Ԃł���B�w���S�����������̂Ń[�~�̐i�ߕ��ɂ��Ęb������B�����l�����ɏo�邾���A�Ƃ������`���������ŏo�Ȃ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ�^����B
�I�ȑԓx�łR�N��������߂����Ă��炢�����Ȃ��̂ŁA�����̂��Ƃ͎����Ńv���O�����𗧂Ăĉ߂����Ă��炢�����̂ł���B�w���Ґl�Ԃɂ͂Ȃ��Ă��炢�����Ȃ��̂ł���B
�@16:00 ����w���̈ψ���ł���B����̃I�[�v���L�����p�X�����Ẳ�c�ł��邪�A�ꃖ����ɊJ�Â����\��ɂȂ��Ă���B
�@�k��B�s�̌����w�ɂ̒S���҂���V�j�A�J���b�W�ł̍u�`�ɂ��Ă̊m�F�̓d�b���������B���C���ő̒����������Ƃ�`���邪�A�X�P�W���[���̕ύX�͓���炵���B�O�����h�X�P�b�`�͓��̒��ɕ`���Ă��邪�A�����͖{�i�I�ɍu�`�̏��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
2006�N10��3���i�j
�@�������P���~�܂�Ȃ��B�P���o�邩�瓖�R�M���o��B��N�͕��ׂ������Ď���܂łɂR�������܂��v�����B��N�̊P�b���i���Ȑf�f�j���]���������߂�B�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��悤�B
�@�Q�����z�m�u�����J���Ă��鑍�����i�w�@�̐l���{�w�̊w����ΏۂƂ��ăA���P�[�g�������s�������̒������ʂ����Q���ꂽ�B���i�擾�̊�]�͂Q�����z�m�A�P�����z�m�A����ɃC���e���A�R�[�f�B�l�[�^�[����ʂɂ���B�命�����R�N���ł���B
���̌��ʂ��݂Ĝ��R�Ƃ���B�P�����z�m���Q�����z�m����ʂɂ��邱�ƂƂƁA�C���e���A�R�[�f�B�l�[�^�[�������Ă��邱�Ƃł���B
���R�Ƃ������R�͏�L�̂��Ƃ͌����܂ł��Ȃ����A��w���w���ƁA���݂̒m���������ł��邱�ƁA���Ȃ킿���w�����獡�Ɏ���܂ŐV�����m�����C���v�b�g����Ă��Ȃ����Ƃɜ��R�Ƃ����̂ł���B
���z�w�Ȃɓ��w���āA���z�ɂ��Ċw�ԂȂ��ŁA���z��������ԁA���Ȃ킿�C���e���A�̗̈���܂݁A�܂��A���z�w�Ȃ̊w�ԗ̈悪������ԁA�O����ԁA�s�s��ԂƂ����l�Ԃ�ΏۂƂ�����Ԃ�ԗ����Ă��邱�ƁA
����ɁA���z�w�Ȃ̑��Ɛ��̊�������ɂ��Ă͎����ƒm�邱�Ƃ��ł���͂��ł���B�w�������̓C���e���A�֘A�̏A�E�ɂ��Ă̒m��������̂��낤���H�܂��Ă�A�C���e���A�֘A�Ŏd�������Ă���L���Ȋ�Ƃ�m���Ă���̂��낤���H
�����炭�A�m���Ă͂��Ȃ����낤�B����������đ�w�֓��w���A������������܂A�E�����߂��ɑ��Ƃ��Ă����w�����������A������m��Ȃ��܂܁A�V�����T�O��g�ɕt���Ȃ��܂܁A������������܂ܑ��Ƃ��Ă����w���������Ȃ����̂������ł���B
�w�������ɂƂ��Ă͌����̖��ł��邪�A�w�������������C���e���A����Ƃ����Ƃ͏��Ȃ��̂ł���B
�C���e���A����Ƃ����Ђ̓J�[�e������ǎ��Ȃǂ̓����ޗ��֘A�̉�Ђ������B�C���e���A������v���鎖�����͍��̏��A�F���ƌ����Ă��ǂ��B
�w�������͂��̂悤�Ȏ�����m���Ă���̂��낤���H�Z��̃C���e���A�ɂ��Ă̓C���e���A���܂v���˗����ꂽ�ꍇ�ɂ͌��z�m���Ɩ�����u���A�J�[�e���A�Ƌ�܂őS�Č��߂Ă��܂����Ƃ������B
���̂܂܂ł́A�V�����T�O�ƌ����̎Љ�ɂ��Ēm�����C���v�b�g����Ă��Ȃ��̂ŁA����͓���ŏI����Ă��܂����낤�B
�@����A�w�������͂R�N������}���鍠�ɂ́A�������I�ȑI��������悤�Ɍ�����B���Ȃ킿�A�f�U�C�����̂ċZ�p���w�ڂ��Ƃ�������]���҂������Ȃ�悤�ɂȂ�B
�R�N�����ɂȂ�ƃf�U�C�����ł��Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ����̌������V�����m�����C���v�b�g����Ă��Ȃ����ƂɋN������̂����E�E�E�E�Z�p�̕����w�шՂ��̂ł���B�܂�A�Z�p���w�ԕ����u�肪����v�A�u��������v�����邩��w�шՂ��̂ł���B
����ɑ��A�f�U�C���̗̈�͌|�p�A�Z�p�A�����𑍍��I�ɑ��������̂ŁA�P�O�O�O�l��������P�O�O�O�̃f�U�C�������݂���悤�ɁA������������肪������Ȃ��B�[�I�Ɍ����A�f�U�C���̓f�U�C������l�̒m�I�\���ł���̂ŁA�m�I�Ȃ��̂�������Ε\�����悤���������A�m�I�f�U�C���͂ł��Ȃ��̂ł���B
�{���͋Z�p���w�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��������A���m��n��o���\�͂�g�ɕt���A���m��n�邽�߂ɋZ�p����g����̂ł���B�Z�p����g����̂͑n���͂ł���B�n���͂��Ȃ���Ύg���闧��ɂȂ邾���ł���B
�Z�p�͑n�����Ɩ��W�ɑ��݂���̂ł͂Ȃ��B�w�������͂��̎�����F�����Ă���̂��낤���H�����l�̗��w���������Z�p���w�ڂ��Ƃ���B�����ł̓\�t�g�����n�[�h����s���Ă���̂��낤���H����Ȏ��͌����č݂蓾�Ȃ��B
2006�N10��2���i���j
�@��T���炸���ƕ��ׂő̒��������B�T�����炾���Ȃ�A�����͊P���o��悤�ɂȂ����B��M������̂��낤�A�ڂ̏œ_���肩�ł͂Ȃ��B�����̂��ƂȂ���A��x�A���ׂ��Ђ��ƂȂ��Ȃ�����Ȃ��B
���߂��Ɍ��������̃��[�����`�F�b�N������B���z�w�Ȃł͂P�E�Q�N���ɂ��Ă͕��S�C��������Ă��邪�A�����S������P�N���̊w�����������ɒ�o�������C�͂��������ۂ֖����o���Ă��Ȃ����Ƃ��������B���C�͂����o�Ă��Ȃ��Ƃ���Ȃ�A�w���ɖ��f��������B
��w�֍s���Ē�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���C�͂��������ۂ֏o���A���X�̎G�p���ς܂���B�؍�����JIA �̃��[�N�V���b�v�Q���҃��X�g���͂��Ă���B�����JIA �֓]������BJIA �̃��[�N�V���b�v�܂łP�����ƂȂ����A�R�N���ɂ͊撣���Ă��炤���ƂɂȂ�B
17:30�@�Ɍ��������o�ċA��̓r�ɂ��B�����̒���߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B